【実践ガイド】介護現場の身体拘束・行動制限をなくす!支援の質向上と虐待防止への道
介護現場において、利用者の尊厳を守り、質の高い支援を提供するためには、身体拘束・行動制限の廃止が不可欠です。しかし、「やむを得ない」状況に直面することも少なくありません。本記事では、身体拘束を減らし、最終的な廃止へと導くための具体的な取り組みや、支援の質を高めるための実践的なヒントをご紹介します。利用者の人権を尊重し、安心安全なケアを実現するための第一歩を踏み出しましょう。
身体拘束・行動制限とは?なぜ廃止が必要なのか
身体拘束とは、利用者の身体や行動の自由を奪う行為であり、原則として禁止されています [1]。これは、利用者の生命、身体、権利の安全を確保しつつ、個人の尊厳を尊重するために重要です。利用者が自分らしく生活できる環境を提供するためには、身体拘束をなくすことが求められます。
やむを得ず身体拘束を行う場合の「三要件」と適切な手続き
原則禁止されている身体拘束ですが、利用者本人や他の利用者の生命・身体が危険にさらされるなど、本当にやむを得ない場合に限り、例外的に認められることがあります。この場合、以下の「三要件」を全て満たし、厳格な手続きを踏む必要があります [2, 3]。
三要件の理解
- 切迫性:利用者本人または他の利用者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い場合 [2]。現場では、常に安心や安全を保障する対応が支援の基準となります [3]。
- 非代替性:身体拘束やその他の行動制限を行う以外に、代替する方法がないこと [2]。切羽詰まった状況では代替案が見えにくくなることがありますが、「わからない状態」を乗り越え、代替案(支援プラン)を実践し続けることが基本です [3]。
- 一時性:本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要があること [2]。「最も短い拘束時間を想定する」ことは、身体拘束の解消を目指す「戒め」であり、「無理だと想定しない」という考えが、実践を継続させていく起点となります [3]。
組織的な決定と個別支援計画への明記 [1, 4]
やむを得ず身体拘束を行う際には、個別支援会議等において組織として慎重に検討する必要があります [1]。この会議には、管理者、サービス管理責任者、虐待防止に関する責任者など、支援方針に権限を持つ職員の出席が不可欠です [1]。
身体拘束を行うことが決定された場合、その身体拘束の態様、時間、緊急やむを得ない理由を個別支援計画に具体的に記載します [1]。これは、身体拘束の原因を徹底的に分析し、解消に向けた取り組み方針や目標とする解消時期を統一した方針の下で決定していくために行われます [1]。
本人・家族への十分な説明と了解 [4]
身体拘束を行う際には、これらの手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分説明し、了解を得ることが必要です [4]。透明性のある説明を通じて、理解と協力を得ることが重要です。
詳細な記録の重要性 [4-6]
身体拘束を行った場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由等、必要な事項を詳細に記録します [4]。この記録は、身体拘束の解除に向けたアセスメントや検証の重要な根拠となり、今後の支援改善に生かされます [4-6]。手書きの対応記録と業務支援ソフトでの記録を併用し、根拠を蓄積する方法も有効です [5, 6]。
事例から学ぶ!身体拘束解除に向けた具体的なアプローチ
事例1:Yさんの居室施錠解除の軌跡 [5, 7-9]
他傷行為や自傷行為が顕著だったYさんに対し、当初は居室の施錠がやむを得ない措置とされていました [7]。しかし、約4年間の取り組みを経て、施錠が不要になるまでの変化を遂げました [5, 8]。
環境調整の工夫
- 玄関前の居室への移動、木製パーテーションによる環境分離 [8]。
- 壁や床への頭突きを防ぐための保護材(クッションやジョイントマット)の取り付け [8]。
- 職員とYさんの居室の間に段ボール箱を緩衝材として配置し、後に移動可能なソフトパーテーションに変更 [8, 9]。
- 職員のユニットへの入室動線を変更し、Yさんのスペースを通らないように工夫 [9]。
段階的な解除と評価
施錠時間を1日2時間程度に統一した記録をこまめに行いながら [8]、「施錠時間について、短くできるのではないか」というケース会議を経て [9]、段階的な解除が試みられました [5, 9]。
- モニター確認での待機時間から段階的に施錠を外す [9]。
- 活動班で使っていたパーテーションが飛び越えられないことに着目し、ユニットでも同様の対応を試みる [9]。
- 居室へ誘導する際に施錠をせず、パーテーションのみで対応 [5]。
- 段階的に汎化する対応:ユニット職員、その他の職員、外部の方がユニットに入る際の施錠を段階的に解除し、それぞれ1ヶ月ごとの評価を身体拘束等適正化委員会で共有しました [5]。
その結果、2022年度にはYさんの居室の中にパーテーションを立てるだけの対応で施錠は不要となり、現在では同意書はあっても施錠実績なく過ごしています [5]。この事例は、非代替性へのアプローチを「鍵からパーテーションへの変化」という支援プロセスの中に見ることができます [2]。
事例2:Tさんの「自分で外せないベルト」から「トイレ排泄」への挑戦 [10, 11]
激しい自傷行為(肛門など)を防ぐため、ズボンのベルトを後ろ向きにつけていたTさん [10]。入所当初は保護者も諦めていたこの対応が、職員の「もうベルト普通でいいんじゃない?」という疑問から見直されることになりました [10]。
職員たちは、Tさんが20歳を超えてから「トイレで排泄する」という課題に挑戦する支援を開始しました [11]。
- 自分または誘導にてトイレへ行く
- 便座に座る
- 居室へ戻る
- 職員みんなで笑顔でたたえる
- アイスクリームを食べる(強化子として)
- 日中活動へ
この日々の定型的な支援を継続した結果、1年後にはトイレに座ることが定着し、うまくできることがほとんどになりました [11]。現在では、Tさんはカードを利用して好きなもの(アイスクリーム、ポテトチップス、コーラなど)を選べるようになり、世界を広げています [2]。
この事例は、三要件の事前検討は甘い部分があったものの、支援開始後も疑問を持ち続け、一時性(最も短い拘束時間を想定)に対してアプローチした点が参考になるとされています [2]。
身体拘束等適正化委員会の役割と効果的な活動
身体拘束の廃止と支援の質向上には、身体拘束等適正化委員会の活動が非常に重要です [1, 3, 4]。委員会は、身体拘束の決定や解除に関する組織的判断、現場へのサポート、研修の実施、モニタリング、記録データの分析などを通じて、施設全体の取り組みを推進します [3, 4]。
チェックリストを活用した組織的な改善 [3, 12-14]
虐待防止委員会で実施されたチェックリストの活用事例からは、組織的な改善に向けた多くのヒントが得られます [3, 12]。
- 「解除が難しい理由」や「工夫できること」を具体的に洗い出す [13]。
- 定期的な話し合いの場を設け、職員間で情報共有や意見交換を促す [13]。
- 「グレーな支援」(ソファで過ごす時間が長い、身だしなみが不十分、威圧的な対応、職員都合の支援など)を認識し、改善につなげる [13, 14]。
- 日常業務の悩みや、利用者の個別ニーズに沿った余暇活動の提供の難しさなど、職員の課題を可視化し、メンタルサポートを含めた改善策を検討する [3, 14, 15]。
委員会の会議においては、チーム全員を信頼し、オープンな議論を心がけ、一人ひとりの意見を否定しないグランドルールが設定され、具体的な改善計画を立てていくことが推奨されます [12]。
支援の質の向上と虐待防止に向けた継続的な取り組み
身体拘束の廃止は、個別支援計画に沿った継続的な支援が基本です [15]。個別支援計画に記載された目標は、単なる備忘録ではなく、利用者と共に達成を目指すものです [15]。身体拘束や行動制限の改善は難しい課題ですが、スモールステップであっても解除できるよう、チーム全体で協力して進めていくことが不可欠です [15]。
支援現場は個別支援計画を意識しながら統一した支援を行い、法人や事業所全体は、身体拘束等適正化委員会を活用してさらなる改善を目指すことが求められます [15]。また、職員のメンタルヘルスサポートも非常に重要であり、全員で「つらさ」を見逃さないようにすることが大切です [3]。
まとめ:利用者の尊厳を守る未来へ
身体拘束・行動制限の廃止は、利用者の尊厳と人権を守り、より質の高い支援を実現するための重要なステップです。組織的な取り組み、厳格な三要件に基づいた判断、個別支援計画に沿った継続的な支援、そして何よりも職員一人ひとりの意識改革と協力が不可欠となります。
本記事で紹介した事例や身体拘束等適正化委員会の活動、チェックリストの活用といったヒントを参考に、皆さんの現場でも一歩ずつ前進していきましょう。利用者にとって真に安心できる、尊厳ある生活の実現に向けて、私たち一人ひとりができることはたくさんあります。
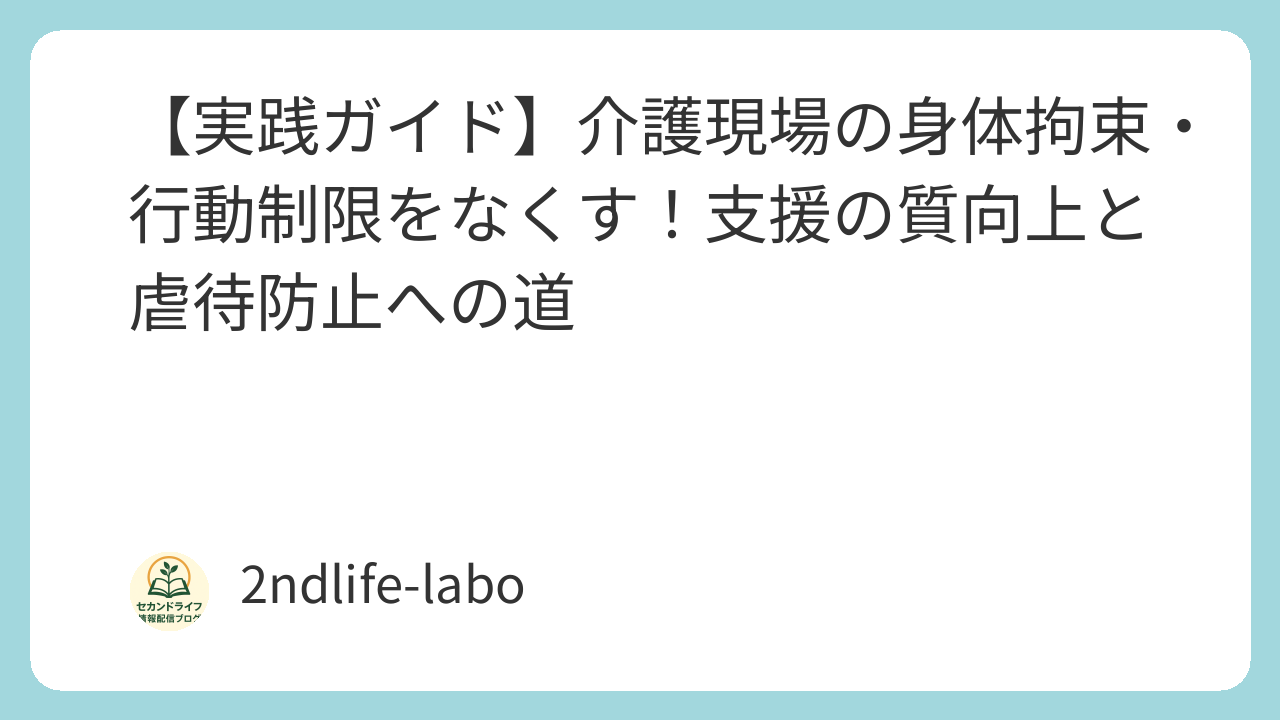

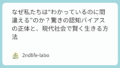
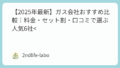
コメント